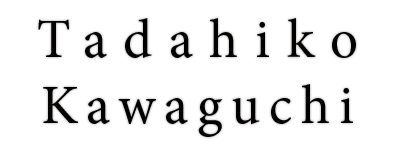8/30 個展会場A STORYにて七梨乃 那由多氏によるギャラリートーク(二回目)を行いました。
以下、当日の模様を七梨乃氏に起こしていただきました。
大変長らくお待たせいたしました。
ギャラリートークの第二回の模様をお届けします。
今回は前半、七梨乃による美術トークが入っており、
後半はそこから発展して、川口さんの作品に対する技術的、精神的な面から、
ここだけのお話をして頂いています。
アートというのは、観るだけでも大いに感動できるのですが、
語れば語るほど、その深みを増していくようで面白いですね。
それを皆で共有していった時に、どこまでいけるのか。
今後が楽しみになるような素晴らしい会でした。
この場を借りまして、あらためて皆様に御礼申し上げます。
それでは、またちょっと長めですが、是非お楽しみ下さい。
文藝サークル『天秤と鏡』七梨乃 那由多
(※以下、可読性のために内容をある程度編集しています。)
川口忠彦氏(以下、川):それでは、始めさせていただきます。
すみません、遅くなりまして。ありがとうございます。
七梨乃那由多(以下、七):では、第二回ギャラリートークを始めていきたいと思います。
まず最初に自己紹介をさせていただきたいと思います。
私、七梨乃那由多(ナナシノ ナユタ)という名前で同人作家をやっておりまして、
自分の文藝サークル『天秤と鏡』でコミティアなどでたまに小説本を出したりしております。
美術がすごく好きで、もともとは美術担当の書店員だったんですけれども、
その流れで美術のツイートをしていたら川口さんに気に入っていただいて、
今回の席を設けていただきました。
前回なんですけれども、タロットについてのお話をいろいろとお伺いしまして、
実際にタロットとは何ぞや?というところから、
「マルセイユ版」と「ウェイト版」の二つの要素を取り入れて、
川口さんなりに現代風に解釈して、
そこに新しく「青い鳥」というものを個人の見解として加えられたんですね。
タロットというのは、人生で必ず出会う22の情景。それに対して、
その時々によって幸せというもの、幸福感というものがどこにどれぐらいあるのか、
その指標として「青い鳥」を加えられたという、それが川口さんの考え方だったんですけれども、
根っこにあるのは、例えば「塔」だったり「死神」だったり、一般的に悪いと言われているものに関しても、
川口さんとしては、ただ“悪い”で終わるのではなくて、次に良いものが来るための「クッション」段階としての、
「塔」だったり「死神」だったりということなんだよ、ということを言いたい、
そのために「青い鳥」という指標を置かれたんだと。
とまあ、前回の話はここまでにしておきまして、
今日はですね、川口さんがゲーム製作の監督をされていた時に作られた、
『ヴィーナス&ブレイブス』というゲームの解説から入っていきたいと思います。
これは僕が本当に……10年前ですかね?
川:11年前ですね。
七:11年前!僕、今年28歳なので、17歳で出会っているんですけれども。
川:一番多感な。
七:一番多感で一番暗黒の時代だったんですけど(笑)、そんな時に『ヴィーナス&ブレイブス』をやって、
本当にこの物語にのめりこんで、ずっと好き好きと言って川口さんを追っかけてきたわけですけれども、
そのゲームについてお話をしたいと思います。
川:ちょうどこちらの三人は、かなりヘヴィな『ヴィーナス』のファンの方なので、
なんの話でも多分わかります(笑)。
七:なるほど。いきなり「メルヴィン」とか言っても伝わるわけですね(笑)。
川:もう全然余裕でわかります(笑)。こちらだけは(笑)。
七:ちょっと、物語のあらすじをさらっていきたいと思います。
『ウェル=バリウスの滅びの預言書』というものがある世界なんですけれども、
その預言書によっておよそ100年間にわたって世界が死んでいくという、
いわば呪いのかけられた世界のお話なんです。
その書の内容を書き換えるために、大精霊――(大)天使のような存在から遣わされた女神アリアと、その血を飲んで不死者となった騎士ブラッド・ボアル。この二人が組んで騎士団を結成して、
100年間世界中を戦い抜くという、そういうあらすじになっています。
で、この二人は不死なんですけれども、実際に騎士団を組むにあたって採用してきた人たちは普通の人間なので、年を取ったら引退するし結婚もするし、100年も戦ってる間にその子供が入隊してきたりとか、
そういうことがあるわけなんですね。そういう風に時の流れと共に移り変わって、
どんどん悪いことが積み重なっていくんだけれども、世代交代を繰り返し、世界中を旅して、
その結果として騎士団の歴史というものが作り上げられていくわけなんですね。「生きた伝説」として。
騎士団で戦った人たちの血族というのが世界中にいるわけで、
その時になって初めて100年間戦い続けてきたブラッド・ボアルの、“俺『たち』はやれるんだ”
っていう言葉が人類全体に届いて、魔物を倒すことができたというお話なんです。
しかし、その時に魂の循環器である『ウルの塔』というのが衝撃で壊れちゃったんです。
『ウルの塔』というのはまあ、黄泉の国のようなもので、死んだ人たちの魂を循環させ自我をリセットして、綺麗な状態にしてまた地上に送るという機械なんですけれども、それが壊れちゃったので、
精霊の皆さんは大変お怒りになって“世界をリセットしてやる!”といい始めたんですけれど、
最終的にブラッドによって神様(大精霊)が殺されたことによって、
神話の時代が終わるというエンディングになっていくわけなんですけれども。
僕はけっこうミーハーだったので、普通の(有名な)RPGをやってきたんです。
ファイナルファンタジーや、ドラゴンクエスト……
ロードス島戦記とか、そういう物語もすごく好きだったんですけど、
『ヴィーナス』をやってすごく衝撃だったのは、神様を殺す、
それ自体はまあまああるでしょうという感じなんですが、
枠を壊すということを物語の中でやっちゃったということが僕にとって衝撃だったんですよね。
最初に買った時に「百年戦うゲーム」というふれこみがあったじゃないですか。
“そうか百年戦うのか、頑張ろう”って思うじゃないですか(笑)。
そしたらそれが全部劇中劇でした、っていうのをやるわけです(笑)。
川:ふふ(笑)。
七:いきなりメタなことをやるわけで、僕は当時そのことにすごく衝撃を受けたんですよね。
それで、その物語を自分なりに解析していった時に、川口さんの思想が見えてきたんですね。
女神アリアと不死者ブラッドは、神様がいなくなって魔法がなくなったので、ただの男と女になり、
その時初めて二人の恋人として結ばれる、っていう終わり方なんですけれども、“そうだよねぇ”と。
僕、最近改めて恋愛論的なもので(『ヴィーナス』を)見直したときに、“あ、そうだわ”と思ったんですが(笑)、人と人……特に男女(恋愛)かもしれませんが……の交際の始まりって、
自分の中の憧れのループを終わらせた時に初めてちゃんと始まるんですよ。
自己完結してて、妄想しているループを終わらせないと始まらない。
それが終わって初めて人として向き合えるようになる、ということも言えるなあと思うんですよね。
自分の中の神話を終わらせるっていうことは、
ある意味で自分の限界を認めることにもなっちゃうわけですよ。
現時点で自分はこういうことができない、ということになってしまう。
でもそこで川口さんが希望として打ち出しているのが、
“でも俺たちには時間があるじゃないか”ということ。
このタロットにしてもそうなんだけども、時間があって、時代が移り変わっていく。
であれば、どこからスタートしたってやっていけるんだから、時間をかければ先に進めるんだから、それでいいじゃないかという、別にどこから始めたっていいじゃんということを仰りたいのかなと思ってまして。
川:おお、なるほどね。
七:前回のギャラリートークの時も、高校野球に出て結局プロになれずに
おでん屋のマスターになったおじさんの話がありましたけれども、“それでいいじゃん”っていうのがあって。
僕はもう、正直前回のトークをやるまでは、
その「おでん屋のマスターになる」ということがちょっと怖かったんですけれども。
やっぱり、プロにはなりたいし(笑)。
川:はいはいはい。せっかく甲子園出たんだったら……(笑)。
七:そうですね(笑)。いけるところまでいきたいじゃないかっていう。
ただ行けなかったというのは悲しいなと。ただ、そこにはそこの風景があるし、
そこから先もあるし……っていうのも(わかったし)、川口さんの仕事は必要になるなぁということを思いました。
で、川口さんの思想というのは基本的にそういうものなんですけれども、
美術という観方から川口さんの仕事を考えていきたいのですが、今お話したとおり、メタ思考の方なんですね。
枠を規定して、それをぶち壊すというところに芸術を持ってきている方なので、必然的に美術自体の話になっちゃうんですが、
今の美術の最前線の話をします。
実は、美術館で観る美術というのは、流行として、終わりつつあります。
その代わりに出てきたのが、『アートフェス』です。
いくつか例を挙げましょう。
『六本木アートナイト』というものがあります(http://www.roppongiartnight.com/2014/)。
これはですね、もうこの前終わってしまったんですけれども、
六本木のクラブ、カフェ、森美術館などの美術館プラス商店街が組んで、
一晩限りのアートと音楽とカフェと商店街の祭典をやるっていうフェスなんですけれども。
それがまず、午後の6時から(翌日)5時までをコアタイムですと言っていて、
もう、全然美術館の……
川:はいはい、逆だ!
七:そうなんですよ、真逆なんですよ。夕方の5時とかに閉まっちゃうのと。
踊ってもいいし、食べてもいいし、その中にアートがあるんです。
あとは『黄金町バザール』(http://www.koganecho.net/koganecho-bazaar-2014/)という、
横浜にある黄金町という商店街なんですけれども、そこもアートフェスをやっていて、
蚤の市、普通のフリーマーケットもやるし、商店街で飯も食えるし、だけどシンポジウムもやってるんです。アートの。
演劇もやっているし。
特徴的なのは、今実際に黄金町で活躍しているアーティストと、海外からの(ゲスト)アーティストが半分半分で出ている。
地元の文化も楽しみつつ、海外の文化に繋がりつつ……でも、「商店街のお祭り」なんですけれどね。
今ヨコハマトリエンナーレというのもやっていて、黄金町はそれと組んでいたりもするわけですけど、
もう関東圏内だけではなくて、飛騨高山もこんど新しいアートフェス(http://hidatakayama-kodamale.jp/)ができましたし、
「アートをアートとして観る」のではなくて、ご飯を食べに来る人はご飯食べに来てるし、
音楽好きな人はそれを聴きに、踊りに来てるし、色んな人がそれぞれの自分の好きな目的のために来ていて、
その脇に「挿絵」としてアートがある、っていう情景が、今のアートの最前線、アートフェスというものになっています。
じゃあどうしてこういうことが起きたのかっていうのには、二つ理由があります。
一つは、地方が抱える問題に対して、民間で解決していこうという流れが出てきました。
地方の問題っていうのは要するに過疎化ですよね。伝統工芸もバンバンつぶれちゃうし、
お年寄りが亡くなったらもうそこでおしまいっていう現実、“介護どうすんの?”とか、
それに対して国が何もやってくれないから、自分たちでやるしかないじゃん、と。
そこで町興しを兼ねてアートと組もう、という流れ。
国が今までそういう地方の問題に対してやってきたのは、いわゆるハコモノ的公共事業ですよね。
ハコモノというのは、もう今のオリンピック(会場)にしてもそうですが、
いきなりでかいものをぼこんと作って、“誰が使うの?”誰も使わないでしょう……と。
あれって結局何が目的だったかというと、莫大な予算を行政に配って、議員には実績、
業者にはカネを配るという、それが目的だった。
だけどもう流石にそれはまずいんじゃ、というのがわかってるから、
プロジェクト自体を自分たちで考えないといけない。誰かにやってもらうのではなく、
その「やり方」から考えないといけないということを皆考え始めたんですよ。
そこでアートというのが、挿絵としての需要が出て、
野心を持った若者もいっぱいいる業界ですから、そういうものと組んでエネルギーを持とうとなった。
もう一つは、美術館で観るという鑑賞のスタイル自体が限界に来ているということ。
“美術館で美術を観ましょう”っていうのには、何かちょっと、構えるところがありませんか?
何々美術館で行われている抽象画の展示を観に行くとか、フェルメールがどうとか、
“絶対勉強しないとわかんないんだろうなぁ”という感じがすごくする。
それってみんなが抱えている問題で、実は『美術館疲れ』っていうのがあるんですよ。
川:へえぇ。
七:こう美術館を回っていると、つまんないデパートを回った後みたいにすごく疲れて、
もう歩いてられないってなってしまうという問題があるんですけど、色んな要素があって。
区が立てた(公立)美術館というのは、地元のお金持ちの趣味の倉庫なんですよ。
常設展という名の倉庫だから、その人の趣味を他の人が観ても全然つまらなかったりとか。
川:はいはい、なるほどねぇ。
七:まず教養を観につけないとわからないというその前提自体が、もうバブルの名残ですよ。
学歴、ステータス重視で、あなたは文化に触れる資格がないですよという呪い。
フェスはそういうところから逃れようとする試みでもあるわけですね。
川口さんのこの展示は、川口さんご自身の作品も展示されているし、
タロットもまた、川口さんの美術作品の一つだけれど、それを遣って占いもやっているし、
この会場もまたお店だから、(雑貨を)買って楽しむこともできるし、色んなことができるじゃないですか。
それって実はスマートなことというか、求められているところなんですよ。
川:時流に合っている?
七:時流に合っているんですよ。それがアートの今の流れなんですよね。
この額にはまった絵なんですけど、美術っていうのはもう、正直死んでるんですよ。
……画家さんを前にして言うのもなんですけれども(笑)。
というのは、ピカソという人が殺しちゃったので。
ピカソというのは『キュビズム』といって、二次元の中に三次元を無理やりやろうとして、
キャンバスの中に3Dモデリングをがんばってやり始めた人だったんですね。
彼の何が一番の偉業だったかというと、
今までは写実主義、印象主義、象徴主義という流れがあったんですけれども、
写実はまず写真みたいにリアルさを追うのが流行りだよねというところがあって、
印象はそのリアルの流れを踏まえて、いや違うでしょ、自分たちの思ったことをそのまま表現できるのが、
絵の技術の最高(の目標)だろうという、写実主義に対する反論としてあって、
今度はそこに象徴主義というのが出てきて、それは違う、皆が共有できる観念を描くというのが、
絵にしかできないことだという、反対、反対、反対という流行の繰り返しだったわけですね。
ある意味でお互いを補完しあっていた。
だけど、ピカソはその流れ自体を否定したわけです。
そのために、枠の中で三次元を描くということをやっちゃって、それが当たっちゃったもんだから、
もうそれ以降の人たちっていうのはとんちを利かすしかないわけです。
一休さんのように……
川:そこから始まってるのね。今の現代美術も。
七:まさにその通りです。現代美術の始祖は『ダダイズム』というのですけれども、
もうそこから変わっていないわけですよね。とんちなんです。
枠の中で勝負をするのではなくて、枠の外で勝負をする。
真っ白なキャンバスを置いて、「ここから観えてきた風景がアートです」とか、
絵の観方そのものでアートをやろうとした。
川:デュシャンとかね。
七:まさに。デュシャンはダダイズムの父なんですが、男性の小便器を逆に置いて、
『泉』という名前をつけて出品したという、まあおかしい人なんですけど(笑)、
観方を変える、それがアートだと。それしかなくなっちゃったんですね。
枠の中でやれることをピカソがやっちゃったから。
枠の中に収まった絵としての美術、というのはもうそんな状況なんですよね。
それを認めようとすると今度は贋作という問題も出てきたりして。
贋作という問題、今出ている美術手帖の贋作特集というのを読んでおぉ、と思ったんですけれども、
例えばフェルメールという中世の画家の贋作で食っていた贋作家もいたんですよ。
面白いのは、“実はフェルメールはイタリアの影響を受けていて、こんな画風にも存在していた”
っていう歴史があったんですけれども、それがもう丸々その人の仕事だったんですよ(笑)。
川:へええ!
七:その人は17世紀の、全然売れてない絵を買ってきて絵の具をこそいだんですよ。
こそいで、それを使って絵を描いた。で、フェルメールの特徴をその絵の中に埋め込んで、
“実はフェルメールはこういう絵に挑戦していた”といって出したら、通っちゃって。
川:はっはっは(笑)。
七:オークションで、やっぱり美術ってやりとりされていたわけなんですけれども、
そこの人たちが世紀の大発見だといって判子を押しちゃったもんだから、それがもう通っちゃって。
それって何故起きたかっていうと、みんながフェルメールを聖人化しちゃったから。
“天才だからなんだってできるだろう、描けるだろう”と。この人は物語を持ってるんだと。
ちょっと前に映画になった『ダ・ヴィンチ・コード』っていう本があって。
『最後の晩餐』という絵の中に実は暗号があって、世界を災厄にみまう陰謀がここから始まってるんだといって、
テレビ番組でやったり、トム・ハンクスが映画をやったりしたんですけれど、
結局画家を神と見て、何でもできるから~という前提を皆が持っていたことによって、
実は美術の本質というのはどんどん汚されていたし、その人が本当に描きたかったものというのを誰も考えない。
だけど担ぎ上げるという時代だったんですけれども、それが壊れつつあるということです。
それに対して、今の川口さんのやり方というのは、とにかく実用主義で、
ご本人がもう、とにかくご自分で描いた絵で生活に直接繋がって行きたい、と考えていらっしゃって、
そういうところに僕は価値があると考えていて。
川口さんの作品を、現代アートの一つの文脈として捉えた時に、
「遊びたい」という気持ちを起こさせるというところに、川口さんの芸術の価値があると思う。
遊びを始めるメディア、というところがあって。
やはりご出身がゲームという総合芸術なんですけれども、前回仰られていたのは、
もっとアートとか純粋な環境音楽の方が自分を癒してくれるだろうし、そういう人も増えるだろうと。
「ゲーム」という現実逃避のハコではなく、
もっと生活とか人生にアクセスできるものを探されて、今回の企画になったわけですけれども、
絵というものから何か物語が始められるというスタンス、これはなかなかないですよね。
表現に実効性を持たせる、ということなんですよね。
今回川口さんがタロットを選ばれたきっかけは、ご自分の表現の幅を広げる、というところでした。
川:はい。きっかけは、そうね。
七:結果的には占術師の方とコラボレーションして、お店ともコラボして、
一つの遊べる場というのを作られたんですけれども、それって既存のメディアミックス的なものではなくて、
あくまで川口忠彦という物語、『ヴィーナス&ブレイブス』でも語られていたし、『セブン』でもそうだし、
それ以前にも語られていた、その物語は終わっていないんですよ。
言ってみれば、この作品たちだって『ヴィーナス&ブレイブス』の続きだとも言えるし、
ある意味、TERROR SQUADさん、マシリトさん(のアートワーク)の方向からもそうだと言えるし。
川:そのマシリトさん、今あそこ(客席)にいらっしゃいます。お久しぶりです(笑)。
七:あっ、そうなんですか(笑)。
美術というご自分のフィールド、ゲーム、アートワークというそれぞれがあって、
でもすべて、「外伝」じゃないんですよ。あくまでこれまでの物語全部、その「本編」が続いているということをすごく感じます。
このタロットでいうと、川口さんは「愚者」を敢えて背負うということをされているのかなと思います。
始まりであり、終わりであるということ。前回光と闇の話をしましたけれども、
光は調和。みんなでなんかしようぜ!という感じ。闇というのは、受け止めるというか、
ある意味調和ではあるんだけれども、現実を分析して、冷静に指摘してくれる存在。
その二つを繋げているんですよね。だから、川口さんの絵というのは「全ての人(の人生)にとっての挿絵」ということが言えるのかなと。
川:うん。そんな気がする。
七:それでちょっと触れたいと思ったのが、『丑の刻参り』という作品がヒルバレースタジオで展示されていましたよね。
川:はい。そうですね。
七:拝見したんですけれども、すごくエンブレムっぽい感じというか、一つの意匠という感じがすごくしたんですが、
あれはtwitterではこれまでのご自分の画風を纏められたと仰っていましたが、
あそこで感じられた、何か手ごたえというか、達成できたというものはあるんでしょうか?
川:空間的に、いわゆるストロングスタイルの絵画の作品と、タロットみたいな平面構成をメインにして、
形の平面的な面白さが割とうまく融合できてきたなという感じ。
それと、ここ数年で、自分の軸足がやはり19世紀美術なんだな、っていうことを強く自覚することが多くて、
それがかなり素直に出てき始めたなと思ったのね。あの枠とか、かなりビアズリーチックだし、
書き文字とかも19世紀末の感じとか、かなり素直にできていって、そういうのが(ある)。
『丑の刻参り』なんで、わら人形を使って呪いをする状況、というのをクライアントさんに言われて書いたんだけど、
それを純日本にするんじゃなくて、わざと和洋折衷のわけのわかんないものにして、
でも形態はできるだけ西洋に寄せて、ちょっと装飾的にするとか、あのバランス感というのが、
今後、絵画的にはああいう方向に行くんだなということ。
本当に絵画とか描くとかそういうところにかなり寄ったところで、自分の今後になりそうなもの。
やっぱりゲームも作ってきたし音楽もやったし、詩も書いて、絵も結構ばらばらな絵を描いてきて、
今後どうなるんだろうって自分でも思ったんだけれども、もしかしたら絵という意味では、
結構一点に向かってんじゃないかな、という手ごたえを感じましたね。
七:かなり集中をしてきたと。
川:そうそう、してきた。
七:なるほど。意匠的なものと聞いて感じたのは、『丑の刻参り』なので、
呪う女の人がわら人形を織っているんですよね。
そのポーズがわら人形を持ってそこから糸がぴゅーっと伸びて、縫っているんでしょうけれど、
そういう瞬間が描かれていますけれど、そのポーズから僕は手仕事に対する愛着っていうのをすごく感じていて、
19世紀美術といえば、ウィリアム・モリスだったりとか、
どっちかっていうと職人さんの技を美術にしていこうという流行があった頃なんです。
模様とか、実際に服にしてもおしゃれだったりとかするわけなんですけれども、
やはりそういうところにリスペクトがあったのかなあとすごく思ったし、
どこか版画的でもあるんだけれど、親しみやすさもあるんだけど、
物語が盛り上がってきたところに、神話に届くような感じもあるんですよ。
呪いをこれからやるぞと。現実的じゃないところに行くんだという、それをすごく感じました。
川:ああ、そうね。確かに確かに。
七:もう一つは『エス』という、ヒルバレースタジオの作品なんですけれども。
珍しく赤基調ですよね。女性の脚、下半身だけが絡み合っているし、彼岸花?が咲いているのが、
もう乱れ咲いて、花弁が乱れ散って、下半身にばあっとかかっているという、
すごいフェティシズムです。個ですよね。線もコミックエッセイのようだし、
エロティシズムというのは新しいなと思って。あれは川口さんの感じでは……ないですよね?
川:そう、多分改めて見てみると、俺って普遍性をやっぱり一番大きなキーワードとして、
とにかく皆が見てかっこいいと思うもの、死神だったらああいうカッコよさだよね。
皆が思う、鎌持って颯爽としているのがカッコいいんだとか、隠者だったらローブ着て篭っている感じとか、
そういうものに竜巻が起こったりとかのワンアイデアを加えてと普遍に向いていたんだけど、
そういえば自分の個体性とか、「自分の」というところから深めて普遍に向かうというのをあまりやったことねぇな、と思って。
やっぱり会田誠を見ていると、彼はもうフェティシズムとか……
七:(笑)そこからですか!僕もう本当にそうだなあ(会田イズム)と思って……(笑)
川:そうそう、でしょう?(笑)もう思いっきりそうで、逆にいうと軽薄な動機って大事だと思っていて。
会田誠を観て「ああなるほどね、じゃあ俺も!」みたいな(笑)。
割とそういうところはライトなんだけど、自分の場合のフェティシズムとか個体性っていうのを、
一回極めてみたらどうなるのかって言うのが『エス』で、
あれは本当に女性の脚に美を見出してる人にとっては“これは綺麗ですね、私気に入りました”って、
男女問わず言ってもらえるんだけど、
それがわかんない人にとっては“なんで脚ばっか描いてんの?”って言われるという、
不思議な反応のある(笑)。俺はもう美を描いているつもりしかなくて、
こんなに「美」だらけの作品はそうないと思ってるんだけども。
七:(笑)僕は脚フェチではなかったから、“うーん、これはどうしたことか”と(笑)。
わからなかったんですけれども。
川:謎だったのね(笑)。そうそう、そういう大きな違いが出る、珍しい作品で、
ちょっと実験的にやってみましたという感じです。
七:面白いですね。まさに会田誠の話をこれからしようと思っていて、
会田誠の補足なんですけれども、美少女をモチーフに描いている人で、
以前六本木の森美術館で展示をしている、現代アートでいうと大御所の方なんですけれども、
結構グロいといえばグロいのが多いですね。美少女の裸がミキサーにかかってるだとか、
江戸時代の巻物なんだけれども、登場人物が全員スク水を着た女子高生だとか、
そういう方なんですけれども。
女体というのはこれまでにもアートワークなど、川口さんの作品の中にも出てきてたんですよね。
バフォメットとかヌードもあったし、だけど、川口さんが使う女体というのは、
前回タロットで「悪魔」におけるバフォメットは主役じゃないんだというお話がありまして、
人間の方が主役で、悪魔そのものよりも、悪魔的なものに自ら飛び込んでいく。
首輪が緩いというのは本当は自分で出られるはずなのに、自ら官能的な部分に落ちていってしまう。
これって悪魔は道具に過ぎなくて、ヌードの使い方もそうだし、
アートワークにも「掴み」的なもので使われてて、僕はエロティシズムを感じなかったし、
だけど『エス』というものは「肉」にすごくフォーカスしていたから、
すごく“肉だなぁ……”と思って。あの心境の変化ってかなり大きかったんじゃないですか?
やっぱり自分の肉体性に目を向けるのってすごく難しいというか、
僕もネガティブな人間で、もともと小説を始めたのって現実を否定したいから始めているわけで、
自分に関する現実というのが全部嫌いなんですけど、
川口さんも「闇」の人だから、そういう部分もありますよね?
川:そうね。そういう自分とか自分の周りのことじゃなくって、
とにかく観ている理想だけを描きたいというのがすごくあって。
でもそっちばっか行っていると……
一個は、タロットをやってたことでそこをクリアできちゃった感じが自分の中であって、
次に行くのはそっちじゃなくて、今までは精神性の一番上の方をやろうとしていて、
今度は一番下の方をやろうとしていて、もう自分の肉体性とか、フェティシズムとか、
逃れようの無い自分のところをやろうとして初めて、次の段階の、
よりアート的なところに行くのかなっていうのははっきり思ってやったところ。
七:バランスを取るために、ということですよね。
川:例えば草間弥生にしても、千住博にしても、やっぱりどっかでブレイクスルーした時に、
必ず自分の個体性とか自分固有の感覚というところに着目した時に、簡単に言うと評価され始めた。
草間弥生は『無限の網』という作品でヒットしたんだけど、ああいう、
その人にしかわからない感覚かもしれないギリギリのところをついた時に、
特に欧米では評価されるんだなあと思って。
そう考えると、自分はそっちはやってない。
おとぎおとぎで、『ヴィーナス』なんかは完全に理想化されたおとぎの話だし。
そうじゃなくて……というのと、やんなきゃいけないっていう固い意志が大きかった。
七:あのヒルバレーに並んでいる作品の中でもかなり攻めている、
もう言ってしまえば殴り込みをかけているようなところがありますよね。そういう動機だったんですね。
草間弥生は水玉模様の……ちょっと前にiidaという携帯電話のデザインもやってましたよね。
あの方はもともと、神経症なんです。本当に夜に網目模様が自分の目に観えてしまうらしいんです。
ずっとそれを抱え込んできたんだけれども、それをあのデザインに落とし込むことができて、
それでブランドが出来上がってきたんです。そういうところが川口さんがこれから挑戦されるところだと。
川:そう。そこには向き合わないと、この先は無いなという感じを強く持ったので。
七:大変ですよね……(笑)というのは、肉体性ってすごく好き嫌いが分かれるから。
『エス』っていう作品そのものについての評価もそうだし、あれは好きな人はすごい好きだけど、
ハマんない人は“えっ”となってしまうから(笑)。
そういうところって普遍的なものと違って、流れを変えてしまうし。
それは大変ですけれど、そこを通らないと……
川:結局目指すところが普遍というのは変わらなくて、ただ今までは普遍を普遍として言っていただけなんで。
すごい厭な言い方をすると、“平和って大事だよね”って言ってるだけな感じがしたの、俺は。
七:ああー!……24時間テレビ的なやつですね?(笑)
川:そんなの皆わかってるし、真実を真実として、真理を真理としてそのまま言ってるだけでは……
命は大切だとか、平和がいいんだとか、戦争は良くないんだとか、そういうことでなしに、
まったく関係ない自分の生活のことを描いているにも関わらず、
その結果、平和が大事だと言えることが、芸術の目的になるのかなというところに到達した。
七:やっぱり美術のクオリティを追究した時に、ただ観て“キレイ”で終わったらそれは良いものとは言えないんですよね。
そこにいたるきっかけというのにはタロットがかなり影響があったんでしょうね。
川:うん、かなりでかいね。
七:ここに描かれているのはやはり真理であるし、普遍性なんですよ。おとぎ話。
だけどそれを実際に使って占いをしたりして、こういうドラマが色々生まれたし、
色んな方面から色んな人が集まって色んなイベントをやるような、
その体験が川口さんのそうした動機を生み出したのかも知れませんね。
川:そういうのもあるかも知れないね。やっぱり次の段階なんだっていうのが強くあったから。
七:僕は川口さんの普遍的な、精神的な部分への取り組みは観てきたんですけれども、
肉体的な、個人的な部分はあまり見えてこなかったんですよね、これまで。
川:そうでしょう。隠してきたからね。一切作品に表れないようにしてきたんで。
美意識の方だけで制御してきたから。その後にそういうもの(肉体的アプローチ)が入ってきて。
七:「お題目」で終わらないために、川口さん自身が表舞台に出て行かないと、
中身が通らなくなってきたということですか。
川:そういう感じがする。
七:昔は僕の中で『ヴィーナス&ブレイブス』のすごい監督さんというイメージでしたけど、
今はもう昼間カレーを食べる人だということを知っているし(笑)。
会場:(笑)
川:ははは(笑)twitterでね。
七:毎日の血圧も知ってるし(笑)。魚を焼く人っていうのも知っているから、
大分もう川口さんの人となりがわかってきているんですよね(笑)。
でもそれもすごく大事なものなんでしょうね。
美術の流行っていうのも「リアル」、ここで実際に話している人のリアルが透けて見えるということに意味があるし、
そこから一つ一つの絵を観た時に、自分たちもここからどうやっていこうかなあ、というのが必要になるでしょうね。
川:一個だけ具体例を挙げると、顔を描く時に、鼻の下の人中はできるだけ省かないように描くようにしていて。
それがあっても美しいように描かないとだめだっていうのが自分の中の基点というか。
これがないとアニメや漫画っぽく、かわいくなりやすい。
鼻も、鼻の穴だけちょんちょんと描けばかわいらしくなりやすいんだけど、
そっちじゃない方向に行きたい。それは必ずあるものだし、それを描いて尚美しいというものをやりたいと思っていて、
そういうのに近い、さっきの話は。
七:難しいですね。少年漫画や少女漫画って顔のパーツをなるべく簡略化しようとするじゃないですか。
造形という面で観た時に、鼻っていうパーツって結構……醜いですよね、正直な話。
ここを隠すだけで結構美しくなる顔っていっぱいあるから。
川:この「星」の人なんかもガリッと描いてあるし、でも“坂本龍一みたいだなあ”とはならず、
……人中描くと坂本龍一に見えてくるんだよね(笑)。もしくはサルやチンパンジー(笑)。
でも美人に見えるっていうのはこだわり。
会場・七:(笑)
川:それがすごい、ミクロな例だけど、個別性というともすれば醜悪な部分を内包しながら、
普遍性という美の部分に至るところの、すごくミクロな例として挙げました。
七:そうですよね。鼻というのはすごく大事な問題だし、
あそこで描くと決めたらその奥の表情を描くしかないじゃないですか。
この人はただの美人です、で終われない。
鼻の穴だけだったら、結構印象だけでごり押せるので、こういう感じの人いるよね~みたいな、
黒木メイサ的だよね~って、あとは目を大きくしておけばいいやみたいな(笑)
だけどあれを描いちゃったらあの人は「あの人」にしかならないから、
ちゃんと役割を持たせてあげないといけないし、ポジションをあげないといけないから、
そういう意味でかなりチャレンジングですよね。
川:すごく地味で自己満足的な部分なんだけど、自分にとってはすごく大事なところ。
七:いやいや、大事ですよ。『青い鳥タロット』の一つ一つの絵柄に説得力があるのは、
そういう技術があるからだと思うし……僕、「力」の女の子がかわいくってタロットを買ったんですけれども。
川:ああ!ありがとうございます(笑)。今回大人気で三枚売れてます。
七:あの子、かわいいですよ。あの子別の何かに出ませんか?(笑)
川:わからない(笑)。機会があればとしか言いようが無いけれども。
七:僕は結構ゲーマーなので、萌えキャラ的なものを見つけると愛を傾けちゃうんですが(笑)。
あの子がすごくいいなと思うのは、隣のライオンにまったく負けてないんですよね。
ライオンがめちゃめちゃキャラ立ってるんですよ。鬣の中に宇宙があって。
宇宙を内包して、そこから輪くぐりじゃないけど出てきてっていう勢いがある。
そういう幻獣を制御している若い女の子なんですけど、ちゃんと力を制御している、
もう一つのバランサーということがわかるから、どうしてかなあとも思ったし。
今後の展開がやはり楽しみなんですけれども、やはり『丑の刻参り』という総決算的なものを展開するのか、
『エス』のようなものをもっと出していくのか、どう考えていらっしゃいますか?
川:多分、これ(ラフマニノフ~)に近い方向に行きつつ、
もうちょっと抽象的な絵になっていく気がしています。
その過程で『エス』っぽさが入ってきたりとか、そういう気がする。
でもそれだけだとただの私的な抽象画で終わるので、
きっとそのへんに『丑の刻参り』的なラインとか19世紀末のテイストが入ってくるんじゃないかと。
言葉で言うと何も思いつかないんだけど、
でも始めると多分そうとしか言えない絵になってくるんだろうという気がしています。
七:うんうん、いやあ、本当にわかりました。
川口さんの中で壊さなきゃいけない枠があって、それに対して色々な取り組み、
『エス』であれば女体などといった生々しい要素が入ってくる。
どんどん肉の中に入っていって、血を流し、血管を通って神話というものに至ろうとするのかもしれません。
……今って何か描かれてますか?
川:描いてない。今これやってるし(笑)。
七:ですよね(笑)。いや、もしかしたらお家で何かやってるのかなと思って(笑)。
川:いやいや、無理無理(笑)。最新作はね、ここで販売しているんですけど(とTシャツを指す)。
個展やりながら唯一描いた絵はこれです。二週間ぐらい前に描いたものなので。
あれも19世紀美術だ俺は、と思って描いていて、ビアズリーっぽさが。
七:これもアートワーク時代の流れはすごくあるんだけれども、
ファッションとして見た時に上からシャツを着ても隠れないんですね。
コンセプチュアルでお洒落だし、ファッション的にも考えられているんだなと思いますね。
川:あと意外と『ヴィーナス』のマークに近くなっちゃったって思う。自分の中でね。
七:ああ!表題の文字に似てるんですね。
川:なんだかんだマシリトのフライヤーやった時の絵にも似ていて、
(アートワークを)飾ってみて“これいいじゃん”と思って。
ローブを着たキャラを描こうと思って。
……すごい仕組まれた宣伝のようにやってるんですけど、全然そうじゃないんで(笑)。
商売っ気なんて何もないんで(笑)。
七:(笑)でもデザインが考えられていて、幅が特に邪魔にならないというのがいいですね。
今たりあさんが着ていらっしゃるような感じになりますけれども。
占術師 たりあさん:これはメンズのSサイズです。
ちなみに、首につけているネックレスはみかみ先生の作品です(笑)。
七:ここでもコラボレーションが(笑)。
川:だんだん通販番組のようになってきたので(笑)、そろそろ締めに入りましょうか。
会場:(笑)
七:やはりこういう実用的なアプローチもあるし、
だけど本質的には川口さんがこれからやられることというのは、
言葉にしちゃうと陳腐なんですけれども、それぞれが持っている妄想を現実化していくってことなんですよね。
そのために必要な外に飛び出したい、もっと自分も遊びたいという、
遊びに行く前のワクワク感、デートの日の朝みたいな、そんな気持ちを表現して下さる方だし、
これからも色んな形で作られていくと思うので、皆さん是非、ご自分のスタイルで結構なので、
これからの川口さんの活動に注目していただければと思います。というところでどうでしょう?
川:素晴らしいです(笑)。通販番組の方には行きたくなかったのでね(笑)。
七:というわけで、第二回ギャラリートークを終えたいと思います。
ありがとうございました!
川:ありがとうございました。